How to stand up
Hello everyone! I am 井手柳雪 (Ide Ryuusetsu).
I am so happy to receive all those videos on Facebook from everyone on TENSHINRYU ONLINE.
Kuwami-sensei and I watch all of your videos with great attention.
Watching everyone’s videos, we catch sight of points to improve about the techniques and shosa (behaviour/performance) as one would expect. About these points to improve, we would like you to see our comments or, whenever the occasion arises, the brush-up/correction videos that we are going to make from now on.
It’s not just you, but we, too, think about the techniques and shosa every day all day.
Training is something that knows no ends. We always look up, always think of what we did wrong today and what we can do to get better, as we keep training.
Therefore we would like you to keep training with us just in the same way so we can all grow and improve together side by side.
Now then, we’ve already explored how to sit (down) before, so today I’d like to explain to you in detail how to stand up.
As for the different ways of standing up, we have one while holding a long sword and one without whilst only wearing a wakizashi, and on top of that the normal way of standing up and another one that is called 提灯立 (chouchindachi).
The former two types and the latter two types make a total of four ways of standing up, which are going to be this time’s topic.
Standing up with 提刀 (sagetou)
Please let me now explain how to stand up with sword in hand.
When we looked at how to hold a katana in an earlier video,
I explained that in their everyday life samurai in ancient times placed their hand beneath the 栗方 (kurikata) when holding the sword and that during training or demonstrations/performances they would hold the tsuba with their right thumb and index finger like this.
For all my following explanations I will do the standing up while holding the tsuba with my right thumb and index finger.
Whether you place your hand below the 栗方 (kurikata) like in ancient times’ daily life or hold the tsuba with your right thumb and index finger makes no difference for how you stand up.
Therefore I’ll do all the explanations with holding the tsuba with the right thumb and index finger.
Well then, I’m now going to explain in detail how to do the standing up.
First, hold the tsuba with your right thumb and index finger.
Then place the sword on your right hip.
Next, while still keeping your knees together, stand up on your toes.
Take half a step forward with your right foot.
Raise your body and withdraw the right foot you brought out earlier.
Lastly, lower both of your hands.
Now, please watch from the side.
Place the sword on your right hip, then stand up on your toes while keeping both knees together.
Take half a step forward with your right foot, stand up, withdraw your right foot and lower your sword.
Since this was just the brief explanation, I’d like to explain what we’d want you to pay extra attention to next.
First of all, whether you match position of the tsukagashira or the tsuba with that of your kneecaps makes no difference for the standing up.
Also, please make sure not to raise your sword too high when putting it on your right hip.
Moreover, letting the saya touch your body and the tsukagashira come right above your right thigh is what you can use as a reference.
Next, when you stand up, please be careful to keep both knees firmly together like this while you stand up on your toes.
Also, when you stand up on your toes, please make sure to keep your upper body straight. We do not bend forward like this.
Keeping both knees together while standing up on your toes, when you bring out your right foot, as you can see here it should go past your left knee a little bit.
If you take too much of a step, you’ll end up getting too close to your company or opponent. Therefore, try to maintain the ma’ai between you and your company/opponent when you stand up.
Put the sword on your right hip, stand up on your toes while keeping both knees together, without bending forward take half a step forward with your right foot, while maintaining the ma’ai so that you wouldn’t get too close to your company/opponent stand straight up and withdraw your right foot.
Don’t bring out your left foot to the front, but in order to maintain the ma’ai between yourself and your company/opponent withdraw the right foot you brought out.
Please keep these things in mind when you practise the standing up.
提灯立ち (chouchindachi)
Next, please let me explain the so-called 提灯立 (chouchindachi – roughly “paper lantern stance”).
Chouchindachi differs from the usual standing up method as it is a method to stand up without bringing out your right foot.
This one is used especially in a situation where you’re already close to your company/opponent and where it’s hence better to not bring out your right foot.
The 提灯 (chouchin) in 提灯立 (chouchindachi) refers to the lighting used in ancient Japan. It’s a lighting that was in fact vertically expandable and contractible like this.
Standing up just like that without bringing out the right foot is what represents the 提灯 (chouchin) in 提灯立 (chouchindachi). And that is why we call this 提灯立 (chouchindachi).
Well then, let’s have a look at the actual movement in Chouchindachi.
As explained before, Chouchindachi is used especially in a situation with close ma’ai, so it’s better to practise it with a hypothetical close ma’ai where you match the position of the tsukagashira with that of your kneecaps for the okigatana.
Grab your sword with your right hand, bring it to your right hip, while you make sure not to bend forward as much as you can, keep both knees together while you stand up on your toes.
This so far is no different from the usual standing up.
From there stand up without bringing out your right foot.
Then lower your sword.
Please watch from the side.
Grab your sword with your right hand, bring it to your right hip, keep your knees together while you stand up on your toes.
From here, lean just a little bit backwards as you stand up without bringing out your right foot
Then lower your sword.
Demonstration
Compared to the usual standing up, Chouchindachi is likely to put more pressure on legs and loins.
However, through practising Chouchindachi you can drill your legs and loins and build up the muscles necessary for other techniques that require you to stand up or move instantaneously.
Therefore, we would like you to not make light of it as a way of standing up and instead practise the form that is called Chouchindachi.
Standing up without long sword
I will now explain how to stand up without holding a long sword while only wearing a wakizashi.
Other than holding or not holding a long sword, there is basically no difference whatsoever.
However, since the hand form is different, I’d like to show you this way of standing up.
While standing up on my toes, I keep my knees together while making sure not to bend forward as much as I can, then I take half a step forward with my right foot, stand up and conclude in this position.
Please pay attention to the hand form. It’s 開手 (hirade).
Demonstration
立ち上がり方
みなさんこんにちは、井手柳雪(いでりゅうせつ)です。
TENSHINRYU ONLINEのメンバーの皆さんがFacebookに動画をあげてくださっていること、とても嬉しく思っています。
鍬海先生と私は皆さんが上げてくれた動画をしっかり見ています。
皆さんの動画を見ると、やはり技や所作に修正すべき点が見受けられます。修正すべき点については、私たちのコメントや、あるいはこれから私たちが折に触れて上げていくブラッシュアップ動画を見て直して頂ければと思います。
TENSHINRYU ONLINEのメンバーの皆さんがFacebookに動画をあげてくださっていること、とても嬉しく思っています。
鍬海先生と私は皆さんが上げてくれた動画をしっかり見ています。
皆さんの動画を見ると、やはり技や所作に修正すべき点が見受けられます。修正すべき点については、私たちのコメントや、あるいはこれから私たちが折に触れて上げていくブラッシュアップ動画を見て直して頂ければと思います。
技や所作の修正は皆さんだけでなく、もちろん私たちも日々常に考えています。
稽古というものには終わりがありません。私たちは常に上を目指し、今日は何が悪かったのか、どのようにしたらもっと良くなるかを考えながら稽古をしていっています。
ですから皆さんも私たちと同様に稽古を続けていっていただき、お互い上達していって頂ければと思います。
稽古というものには終わりがありません。私たちは常に上を目指し、今日は何が悪かったのか、どのようにしたらもっと良くなるかを考えながら稽古をしていっています。
ですから皆さんも私たちと同様に稽古を続けていっていただき、お互い上達していって頂ければと思います。
さて、以前座り方について解説いたしましたが、今日は立ち上がり方について詳しく解説していきたいと思います。
立ち上がり方は大刀を持っている状態での立ち上がり方、大刀を持たずに脇差だけ腰に差している状態での立ち上がり方の二種、また通常の立ち上がり方と提灯立(ちょうちんだち)と呼ばれる立ち上がり方の二種があります。
前者の二種、後者の二種、合わせて四種の立ち上がり方について今回
は説明していきます。
立ち上がり方は大刀を持っている状態での立ち上がり方、大刀を持たずに脇差だけ腰に差している状態での立ち上がり方の二種、また通常の立ち上がり方と提灯立(ちょうちんだち)と呼ばれる立ち上がり方の二種があります。
前者の二種、後者の二種、合わせて四種の立ち上がり方について今回
は説明していきます。
提刀(さげとう)での立ち上がり方
手で刀を持っている状態での立ち上がり方について説明いたします。
以前の動画で刀の持ち方について説明した際に、
侍(さむらい)は往時の日常生活では栗方(くりかた)より下に手を掛けて刀を持つ、
また稽古中や演武中ではこのように右手の親指で鍔を控えて刀を持つ、と説明しました。
これから立ち上がり方について説明する際には、全て右手の親指で鍔を控えた状態で行います。
往時の日常生活のように栗方(くりかた)より下に手を掛ける刀の持ち方、あるいは右手親指で鍔を控える持ち方、いずれも立ち上がり方には違いはありません。
そのため、これから全て右手の親指で鍔を控えた状態で立ち上がり方について説明していきます。
以前の動画で刀の持ち方について説明した際に、
侍(さむらい)は往時の日常生活では栗方(くりかた)より下に手を掛けて刀を持つ、
また稽古中や演武中ではこのように右手の親指で鍔を控えて刀を持つ、と説明しました。
これから立ち上がり方について説明する際には、全て右手の親指で鍔を控えた状態で行います。
往時の日常生活のように栗方(くりかた)より下に手を掛ける刀の持ち方、あるいは右手親指で鍔を控える持ち方、いずれも立ち上がり方には違いはありません。
そのため、これから全て右手の親指で鍔を控えた状態で立ち上がり方について説明していきます。
では実際に立ち上がり方について詳しく説明していきます
まず右手の親指で刀の鍔を控えます。
そして刀を右腰につけます。
次に両膝を閉じながら、つま先立ちになります。
右足を半歩前に出します。
体を起こして立ち上がり、先ほど前に出した右足を後ろに引きます。
最後に右手、左手を下ろします。
まず右手の親指で刀の鍔を控えます。
そして刀を右腰につけます。
次に両膝を閉じながら、つま先立ちになります。
右足を半歩前に出します。
体を起こして立ち上がり、先ほど前に出した右足を後ろに引きます。
最後に右手、左手を下ろします。
続いて横からご覧ください。
刀を右腰につけ、両膝を閉じながらつま先立ちになります。
右足を半歩前に出し、立ち上がり、右足を後ろに引き、刀を下ろします。
刀を右腰につけ、両膝を閉じながらつま先立ちになります。
右足を半歩前に出し、立ち上がり、右足を後ろに引き、刀を下ろします。
概略を説明いたしましたので、次に特に注意してほしいことについて説明していきます。
まず、鍔を膝頭の位置に合わせた刀の置き方、また柄頭を膝頭の位置に合わせた刀の置き方、どの刀の置き方でも立ち上がり方は共通で、違いはありません。
まず、鍔を膝頭の位置に合わせた刀の置き方、また柄頭を膝頭の位置に合わせた刀の置き方、どの刀の置き方でも立ち上がり方は共通で、違いはありません。
そして刀を右腰につけるとき、あまり刀を上げすぎないようにしてください。
また、鞘を自分の身体に付くほどにする、刀の柄頭を右腿の上にくるほどにするのが刀の位置の目安です。
また、鞘を自分の身体に付くほどにする、刀の柄頭を右腿の上にくるほどにするのが刀の位置の目安です。
次に立ち上がる時、つま先立ちになりながら、このように両膝をしっかりと閉じることに注意してください。
また、つま先立ちになるときに、真っすぐ身体を立てるようにして下さい。このように前傾してはいけません。
また、つま先立ちになるときに、真っすぐ身体を立てるようにして下さい。このように前傾してはいけません。
つま先立ちになりながら両膝を閉じ、右足を前に出していく際、ご覧いただいているように右足のつま先が左足の膝を少し超えるくらい、これが右足の位置の目安となります。
このように大きく前に右足を出してしまうと、相手に近づき過ぎてしまいます。そのため、相手と自分との間合いを保ちながら立つように心がけて下さい。
このように大きく前に右足を出してしまうと、相手に近づき過ぎてしまいます。そのため、相手と自分との間合いを保ちながら立つように心がけて下さい。
刀を右腰につけ、
両膝を閉じながら、つま先立ちになり、
前傾はせず、右足を半歩前に出し、
相手に近づき過ぎないように間合いを保ちながら、
まっすぐ立ち上がり、右足を引きます。
左足を前に出すのではなく、相手と自分との間合いを保つため、
前に出した右足を後ろに引きます。
両膝を閉じながら、つま先立ちになり、
前傾はせず、右足を半歩前に出し、
相手に近づき過ぎないように間合いを保ちながら、
まっすぐ立ち上がり、右足を引きます。
左足を前に出すのではなく、相手と自分との間合いを保つため、
前に出した右足を後ろに引きます。
これらの注意点を意識して、立ち上がり方を稽古して下さい。
提灯立ち(ちょうちんだち)
続いて提灯立(ちょうちんだち)という立ち上がり方について説明いたします。
この提灯立は先ほど説明致しました通常の立ち上がり方とは違い、右足を前に出さずに立ち上がる方法です。
特に相手との間合いが近い状態、右足を出さない方が良いような状況でこの提灯立が使われます。
提灯立の提灯は往時、日本で使われていた古い照明のことを指します。提灯はこのように上下に伸び縮むことが出来る照明です。
この提灯立は先ほど説明致しました通常の立ち上がり方とは違い、右足を前に出さずに立ち上がる方法です。
特に相手との間合いが近い状態、右足を出さない方が良いような状況でこの提灯立が使われます。
提灯立の提灯は往時、日本で使われていた古い照明のことを指します。提灯はこのように上下に伸び縮むことが出来る照明です。
提灯立の提灯というのは足を前に出さずにそのまま上に立ち上がる姿を表しています。ですから、この立ち上がり方のことを提灯立と呼びます。
それでは実際の提灯立の動作について説明していきます。
先ほど説明した通り、提灯立は特に間合いの近い状況で用いられますので、最初に刀を置くとき、柄頭と膝頭の位置を合わせる、間合いの近い状況を想定して稽古を行うと良いでしょう。
先ほど説明した通り、提灯立は特に間合いの近い状況で用いられますので、最初に刀を置くとき、柄頭と膝頭の位置を合わせる、間合いの近い状況を想定して稽古を行うと良いでしょう。
右手で刀を持って右腰に付け、極力、前傾しないようにしながらつま先立ちになりつつ、両膝を閉じます。
ここまでは通常の立ち上がり方と同じです。
そこから足を前に出すことなく、上に立ち上がります
そして刀を下ろします。
ここまでは通常の立ち上がり方と同じです。
そこから足を前に出すことなく、上に立ち上がります
そして刀を下ろします。
横からご覧ください
右手で刀を持ち、右腰につけ、
つま先立ちになりつつ、両膝を閉じます。
ここから、やや後ろに身体を傾けながら、足を出さずに立ち上がっていきます。
そして刀を下ろします。
右手で刀を持ち、右腰につけ、
つま先立ちになりつつ、両膝を閉じます。
ここから、やや後ろに身体を傾けながら、足を出さずに立ち上がっていきます。
そして刀を下ろします。
実演
この提灯立は通常の立ち上がり方と比べて足腰に負担がかかりやすいものになります。
しかし、提灯立を稽古することによって、他の技法で用いられている咄嗟に立たなければならない、咄嗟に行動しなければならない動作に必要な足腰、筋肉を鍛えることができます。
ですから、立ち上がり方といえども軽んじず、提灯立という立ち上がり方を稽古して頂ければと思います。
しかし、提灯立を稽古することによって、他の技法で用いられている咄嗟に立たなければならない、咄嗟に行動しなければならない動作に必要な足腰、筋肉を鍛えることができます。
ですから、立ち上がり方といえども軽んじず、提灯立という立ち上がり方を稽古して頂ければと思います。
大刀がない時の立ち上がり方
大刀を持っていない脇差のみ差した状態での立ち上がり方について説明します。
この立ち上げ方は大刀を持っているか持っていないか、くらいの違いしかありません。
しかし手の形は違うので、実際に立ち上がり方を示していきたいと思います。
つま先立ちになりつつ、極力前傾しないようにしながら両膝を閉じ、
右足を半歩前に出し、
立ち上がり、この状態で終わります。
手の形に注意して下さい。開手(ひらで)という形になります。
この立ち上げ方は大刀を持っているか持っていないか、くらいの違いしかありません。
しかし手の形は違うので、実際に立ち上がり方を示していきたいと思います。
つま先立ちになりつつ、極力前傾しないようにしながら両膝を閉じ、
右足を半歩前に出し、
立ち上がり、この状態で終わります。
手の形に注意して下さい。開手(ひらで)という形になります。
実演

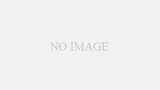
コメント