蝿払突
This is a beginner’s kodachi battou technique in zahou.
It’s a technique that acts as a counterpart to 古伝 (koden), the beginner’s 達磨抜 (darumanuki) from 胡坐 (koza) and the beginner’s 嚔抜 (kusamenuki) alias 閊太刀 (tsukaedachi) from 立合抜剣 (tachiaibakken).
Battou with the kaisho 守 (shu)
Well then, let’s perform the technique called 蝿払突 (haebaraidzuki).
Haebaraidzuki is the foundation of 防刀 (boutou) of zahou.
The 蝿 (hae) in 蝿払突 (haebaraidzuki) refers to the insect the fly.
The naming 蝿払突 (haedzukibarai – “fly swatting strike/stab”) comes from the striking movement as if one were to swat a fly flying around.
Well then, let’s do it!
Let’s have a look at the technique.
The opponent comes with a cut from the side.
At that moment, as I lean forward a bit, I do the battou and at the same time receive the opponent’s sword. At this time, I slightly turn around our body.
Having driven away my opponent’s sword, I go into 跪坐 (kiza) and thrust my sword into them.
Here my knees are closed. I add my left hand to my right elbow as support to stabilize it.
After stabbing the opponent, as I bring out my right foot, I run up to my opponent.
After that, I back off by at least six shaku (ca. 180 cm).
Once I’ve backed off, I do the noutou. We’ll omit that.
Explanation with opponent
So, let’s perform the technique with an opponent.
The maai to the opponent is 信の間 (shin no ma), about 120 cm.
The opponent can either attack with a wakizashi or a daitou, but for beginners let’s go with the wakizashi.
So then, let’s look at the actual attack from an opponent.
My opponent will draw his sword and cut from the side.
Let’s have a look at where he’s cutting.
He is aiming at my shoulder, around my elbow, my neck, my eyes, around my temple etc. As beginners you can just go for the shoulder.
Then, let’s actually have a look at it.
First, my opponent reaches for his sword about to do the battou.
In response I, too, go on and do the noutou.
Since he is cutting from the side, I bend my body a little and catch his sword.
Then I get up on my knees, assume 跪坐 (kisa), turn over the sword from left and stab his shoulder.
After that, I run up to him blocking him.
And then back up and to the noutou.
Demonstration with 殺守剣 (sasshuken)
Now, let’s have a look at some important things in detail.
First the positioning when drawing the sword.
Please be careful not to draw the sword to the front. Also, please make sure to not draw it off to the side too much. Draw the sword in the direction it’s pointing to.
Then, as for the right fist’s positioning, if you draw the sword upwards, the approaching opponent’s sword will just hit your right fist. Because of that, when drawing the sword please make sure to not bring your right fist up high.
Let’s have a look at how to receive the attack.
First, when catching the attack, you do so by twisting your body to the right a bit.
The positioning of your right upper arm is important here. Make sure to bring your right upper arm right next to your body. By doing so, you can prevent your armpit from opening up.
Next up is the positioning of the right fist. It’s positioned slightly next to the right knee around here. Please be careful not to let it go too far in- or outside. Also be careful not to bring it out too much to the front either.
Next, the angle of the right wrist when receiving the attack. Please be careful to not bend it to the inside. The right wrist is supposed to be almost straight.
Next, the positioning when catching the opponent’s sword. In Tenshinryuu we divide the sword into three parts, starting from the kissaki we call them 殺刀 (sattou), 制刀 (seitou) and 防刀 (boutou). When catching the opponent’s attack, we use the first third from the tsuba, in other words the 防刀 (boutou) to catch their sword.
When receiving the opponent’s attack, make sure to fend off their sword with that 防刀 (boutou) between the 裏鎬 (urashinogi – the ridges on the right side of the sword) and the 峰 (mine) or back of the sword. At this time, as explained before, if you twist your wrist too much to the inside, you’ll end up receiving the opponent’s sword completely with the 峰 (mine) and potentially get your sword damaged or fail to defend against the attack. Therefore, please be sure to use the part between the 裏鎬 (urashinogi) and the 峰 (mine).
Let’s have a look at the next
First up, the stance. Close up your knees and get up on your toes. We call this 跪坐 (kiza). Put both legs firmly together and “stand up” assuming 跪坐 (kiza).
Next, the stabbing method. When stabbing, do so by twisting the sword from the left side. At this time, add your left hand to your right elbow as support. Please make sure not to grip the right elbow with your left hand.
Let’s have a look at the positioning when stabbing. I’m twisting my sword from here.
For my stab, I’m aiming at the upper part of his right breast underneath his clavicle.
When stabbing, you might think that his sword staying here is dangerous and outright scary. However, in practice, as soon as I hit his sword with mine, I use that force and thrust right into him. Thus, even if his sword were to remain, it wouldn’t be able to harm me whatsoever.
Especially when performing the technique slowly, since the opponent’s sword easily ends up staying here, you might end up being scared by that sword and receive it forcefully, push it out too far or throw out your sword too much and end up wrapping around the opponent’s sword.
If that happens, your counterattack might end up being too late or the opponent might end up changing up their attack like this. Therefore, even when performing the technique slowly, please be careful to properly stick to the correct form of receiving the attack.
Battou with the sousho 離 (ri)
蝿払突
これは坐法 小太刀における初学の抜刀技法です。
古伝、胡坐(こざ)における初学 達磨抜(だるまぬき)、立合抜剣(たちあいばっけん)における初学 嚔抜(くさめぬき)、別名閊太刀(つかえだち)と対をなす技法となります。
楷書(守)での抜刀
それでは蝿払突という技を行っていきます。
蝿払突は坐法の防刀(ぼうとう)の基本になります。
蝿払突の「蝿」は、虫の蝿を指しています。
この飛んでいる蝿を払うようにして、突いていく、という動作から蝿払突という名前がついています。
それではやっていきましょう。
技を見ていきます。
相手が横から切ってきます。
その際、若干前かがみになりながら抜刀していき、また抜刀と同時に相手の刀を受けます。このとき、少し身体を後ろに反ります。
相手の身体を払ったら、跪坐になりつつ、相手に刀を突きこみます。
この時、両膝は閉じます。左手は右ひじを支えるように添えます。
相手を突いた後、右足を前に出しながら、相手を詰めます。
詰めた後、六尺(180cm)以上下がります。
下がったら、納刀します。納刀は省略します。
対者をつけての解説
では相手をつけて技法を行っていきましょう。
対者との間合いは信の間、約120cmです。
相手の攻撃は脇差、あるいは床に置いている大刀、どちらでも構いませんが、初学のうちは脇差が良いでしょう。
では、対者の実際の攻撃を見ていきましょう。
対者は刀を抜き、横から切ってきます。
切る場所を見ていきましょう。
切る場所は肩口、肘の辺り、首、目、こめかみのあたりなどを狙ってきます。初学のうちは肩口の辺りを狙うと良いでしょう。
では、実際に見ていきましょう。
まず、相手が刀に手を掛け、抜刀しようとします。
それに合わせて、自らも抜刀していきます。
相手が横から切ってくるので、自分は若干身体を反らせながら、相手の刀を受けます。
受けた後、膝立ちになり、跪坐になりつつ、左側から刀を返して、相手の肩口を突いていきます。
突いた後、相手を詰めます。
詰めた後、後ろに下がり、納刀します。
殺守剣での実演
細かい注意点を見ていきましょう。
まず刀を抜く位置です。
刀を前に抜いていかないように気を付けてください。また、あまり横に抜きすぎないようにしてください。刀は差している方向、すなわち差しなりに抜いていきます。
また右拳の位置ですが、刀を上に抜いていってしまいますと、自分に迫ってくる相手の刀の位置に、右拳が来てしまいます。そのため、刀を抜くときは右拳をあまり高くしないようにしてください。
受け方を見ていきましょう。
まず受けるときは、身体を若干右側に捻るようにして受けます。
この時の右上腕の位置が大事です。右上腕は自分の身体の真横に来るようにします。そうすることで、脇が開いてしまうのを防ぐことができます。
次に右拳の位置です。右拳は自分の右膝の若干横、この辺りの位置に来ます。内側に入り過ぎてしまわないように、また外側に大きくずれてしまうことのないように気を付けてください。また右拳が前にも出ないように気を付けてください。
次に、受けるときの右手首の角度です。右手首を内側に曲げないように気を付けて下さい。右手首はほぼ真っすぐになります。
次に、相手の刀を受ける位置です。天心流では刀を3分割に分け、切っ先から殺刀(さっとう)、制刀(せいとう)、防刀(ぼうとう)と呼んでいます。相手の攻撃を受ける刀の位置は、刀の鍔の部分から約3分の1までの部分、すなわち防刀の部分で相手の刀を受けます。
相手を攻撃を受けるときは、その防刀の裏鎬から峰にかけて、相手の刀を受け外すようにします。この時、先ほど説明したように、手首が内側に曲がってしまうと相手の刀をもろに峰だけで受けてしまうことになり、刀の損傷や受けの失敗につながります。そのため、裏鎬から峰にかけて受けるようにしてください。
次の注意点を見ていきましょう。
まず立ち方です。膝を閉じて、つま先立ちになります。これを跪坐(きざ)と呼びます。両足をしっかりつけて、跪坐になって立ちます。
次に突き方です。突く時は、左側から刀を返して突いていきます。この時、左手を右肘に添えます。左手で右肘を握らないようにしてください。
突く位置を見ていきます。ここから刀を返していきます。
突く位置は、相手の右胸上部、鎖骨の下辺りを狙って突いていきます。
突く時、ここに相手の刀が残っていることを危険視したり、怖いと思ってしまうことがあります。しかし実際には、相手の刀が自分の刀に当たるがいなや、その力をもらって相手に突きこんでいます。そのため、相手の刀が残っていたとしても、その刀は自分に害を与えることはありません。
特にゆっくり技法を行う場合、相手の刀がここに残りやすいため、その刀を怖がってしまい、強く受けてしまったり、大きく受け過ぎてしまったり、また刀を倒し過ぎて相手の刀を巻き込んでしまったりします。
このようになってしまうと、反撃の突きが遅れてしまったり、またこのように相手の攻撃が変化してしまったりする可能性があります。そのため、ゆっくり技法を行うときも、しっかりと正しい受けの形を守るように気を付けてください。
草書(離)での抜刀

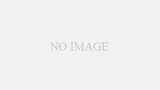
コメント