Kochô-Musubi
This is the usual tying technique for the 下緒 (sageo) of a 大刀 (daitou) in Tenshinryuu.
The length of a daitou’s sageo in Tenshinryuu is six shaku (ca. 180 cm).
I am now going to explain the tying technique for the sageo.
下緒 (sageo) is what we call the string that is attached to a part of the saya called 栗形 (kurigata).
I’m going to explain tying technique to tie this string.
And in the end I’m also going to explain the tying technique to attach it to the daitou.
Firstly, we call this form of the sageo 胡蝶結 (kochoumusubi) in Tenshinryuu. In general it’s just called 蝶結 (choumusubi), but in Tenshinryuu we use the name 胡蝶結 (kochoumusubi) (TL note: both roughly translate to “butterfly knot”). The tying technique is basically the same as how it’s generally done.
Well then, let’s actually do it.
Demonstration
All right, let’s examine how to actually tie the knot.
First of all, please have a look at this one. As this shape resembles that of a butterfly, we call it 胡蝶結 (kochoumusubi – “butterfly knot”). Generally it takes the name of 蝶結 (choumusubi – also “butterfly knot”).
If give this loose end here a strong pull, you will untie it. And if you keep going like this, you’ll be able to undo the knot entirely in a neat manner.
Now, let’s have a look at how to actually tie the knot.
Go along the 下緒 (sageo) from the 栗形 (kurikata) and halve it neatly.
Then let the two overlap and form it like this.
As for how to place the sword, make sure the blade faces yourself and the tsukagashira is on the right. Please start working from there.
Bring the two cords to the right and wrap them around the saya once.
After that, make a loop.
Then let that one go between saya and sageo.
Next, fold it over to the left-hand side.
After folding it over, wrap it once more around the saya.
Once you’re here, again, make a loop and stick it through between saya and sageo.
Fold the rest of the sageo and make another loop. This one goes through the two loops you’ve just made.
That’s it.
During the whole procedure the two loops might come loose.
In that case, you can also simply stick a pen or some other cylindrical object through the loops, so you wouldn’t have to worry about them coming loose.
Once you’ve gotten the third loop through the first two, the basic shape of it is done.
However, since it’s still all loose, we have to tighten it up.
Starting from the root, pull and tighten the sageo all the way down.
If you repeat this several times until it’s super-tight, it won’t come off easily.
Then, as for this loop, it depends on how long the remaining part of the sageo is, but if you make it too big, it will end up obstructing you when you’re operating the sword – therefore, please don’t make it too big.
On the other hand, if it’s too small, the sageo might end up coming off easily, so I can’t say that good either.
This is what it should look like in the end.
The tying technique in case of a long sageo
Please have a look at this. As the sageo is extremely long, there is too much left over.
Even if we make the loops bigger, it’s still too long and your fingers easily get caught in the too big loop and it gets harder to use your sword.
In such a case of a long sageo, the tying method stays the same, but the form is a little bit different. I’ll explain it now.
First, make the same shape. Let the two cords overlap, make a loop and stick it through.
After that, repeat the procedure and make the same shape over and over again.
Fold it over once more to the right-hand side and wrap it around the saya.
Then make another loop and pass it through.
Repeat this procedure as you see fit for the length of the sageo.
Since in the case of Tenshinryuu we put a lot of emphasis on sayabiki, if we were to make three loops, we would make two on the right- and one on the left-hand side.
In case it’s even longer, we’ll make two on both sides.
If it’s even longer than that, we’ll go with three on the right and two on the left.
And if it’s even longer again, just cut the damn thing already.
In this case here, fold it over to the left and wrap it around the saya once.
Make another loop and pass it through.
If you end up making it tight on this level, you won’t be able to stick through the final loop, so please be careful to make it rather loose.
Then make another loop here and pass it through.
After that, just like in the basic tying method in the beginning, tighten up everything little by little.
Generally speaking, it’s important to keep the two parts of the sageo completely overlapping each other when tying them up.
Please be sure that it doesn’t get out of shape as you proceed to tighten everything up.
Just like this, we’ve made two loops on the right and one on the left.
Please make sure to adjust it like this according to the sageo’s length.
The case of an untied sageo
Following up, please allow me to explain how to handle the sageo if it’s not tied.
In Tenshinryuu, the Grandmaster of the Eighth Generation Ishii Seizou-sensei has taught us: “The sageo for a warrior/samurai is no different from a necktie. When attending at a castle or in general, having thy sageo tied is proper etiquette.”
However, there are actually cases of having an untied sageo. Even when it’s untied, there is a way to handle the sageo, so please allow me to explain.
First of all, let’s untie the sageo in 胡蝶結 (kochoumusubi).
The next thing is extremely important. Wrap the overlapping sageo once around the saya. Then stick it through the gap between itself and the saya.
This is an extremely important procedure. If leave it out and the sageo gets caught somewhere, it might get pulled off the kurikata entirely. Also, the sword may become insecure, so always wrap the sageo once around the saya before moving on.
After that comes only wrapping and tying the end of the sageo.
Let the upper end go around the lower one, then pass it through.
Just tie it like this, that’s it. Lastly, please match the lengths of the sageo.
This is an extremely simple method. This is how you handle an untied sageo in Tenshinryuu.
If the knot is too close to the end, it might come loose and undone entirely, so it’s better to tie it at the very least two or three sun in (about 6 to 9 cm).
Actually, I think it might be better to tie this one a little bit higher. For example about this height should be fine.
If anything happens this might get pulled out and come off, so in a case of emergency you immediately remove the sageo from the saya and use it.
This has been procedure in case of an untied sageo.
胡蝶結
これは天心流において、大刀の下緒(さげお)で通常用いる結束法(けっそくほう)です。
天心流における大刀の下緒の長さは六尺(180cm)となります。
これから下緒の結束法について解説を行います。
下緒とは、鞘の栗形(くりがた)と呼ばれる部分に通している紐のことを言います。
この紐の結び方、結束法を解説していきます。
最初にこの大刀における結束法を解説していきます。
まず、この下緒の形を天心流では胡蝶結(こちょうむすび)と呼びます。一般的には、この形を蝶結(ちょうむすび)と呼びますが、天心流では胡蝶結と呼びます。結束法は一般的に行われているものとほとんど変わりません。
では実際にやっていきます。
実演
では実際の結び方を見ていきます。
まずこの形をご覧ください。これが蝶のような形であることから、胡蝶結と呼びます。一般には蝶結と称されます。
特にこの先端部分を強く引くと、外れます。さらにここから外すと、奇麗に下緒を解くことができます。
では実際の結び方を見ていきましょう。
栗形に通した下緒を奇麗に半分にします。
そして二本を重ねてこの形にします。
刀の置き方は刃を自分に向けるようにし、柄頭が右側を向くようにします。そこから作業を始めるようにして下さい。
二本を右斜めに持っていき、まず鞘に一巻します。
一巻した後、二つ折にし、輪を作ります。
輪の先端部を下緒の根本部分、鞘と下げ緒の間に通します。
次に、左斜めに折り返します。
折り返しましたら、同じく鞘に一巻します。
ここまで出来たら、同じように輪を作り、その輪の先端部を鞘と下緒の間に通します。
残りの下緒を折り、同じように輪を作ります。その輪の先端部を、今作りました二つの輪の間に通します。
手順はこれだけです。
この作業中に二つの輪がほどけてしまう危険性があります。
そのような場合は、ペンなどの棒状のものを二つの輪に通しておくと、ほどける心配がないので良いです。
二つの輪に通すと、基本的に形は完成です。
しかしまだまだ緩いので、これをきつくしなければなりません。
下緒の根本部分から順番に絞っていきます。
これを何度か繰り返していけば、非常にきつくなるので、簡単にほどけることはありません。
そしてこの輪の部分は、下緒の余りの長さにもよりますが、あまり大きい輪を作ってしまうと、刀を扱う際に支障をきたしてしまうことがあるため、あまり大きくしないでください。
逆に小さくし過ぎてしまうと容易く下緒がほどけてしまいますので、それも良いとは言えません。
これが仕上がりの形となります。
下緒が長い場合の結束法
ご覧頂けますでしょうか。下緒が非常に長いため、余っています。
輪を大きく作ったとしても、やはり非常に長く、また輪の部分が大き過ぎるため指に引っ掛かりやすく、刀も扱いにくくなります。
このように長い下緒を用いる場合、同じ結び方になりますが、少しだけ形が変わります。それについて解説していきます。
最初は同じ形になります。二本を重ねて輪を作り、通します。
この後、この作業を繰り返して、同じ形をいくつか作ります。
もう一度右斜めに折り返し、鞘に一巻します。
そして同じように輪を作り、通します。
この作業を下緒の長さに見合った分だけ繰り返していきます。
天心流の場合、鞘引きを非常に重視しますから、全体で三回作業をするのであれば、作業している自分側から見て右側を二回、左側を一回行います。
さらに長い場合は、右側を二回、左側を二回行います。
それでも長ければ、右側を三回、左側を二回行います。
あまりにも長ければ、下緒を切った方が良いでしょう。
ここで左に折り返し、鞘に一巻します。
同じように輪を作り、そして通します。
この段階できつくしてしまうと、最後に通すことができないので、あまりきつくしないように気を付けて下さい。
そしてここで同じく輪を作り、これを通していきます。
後は、最初の基本の結び方と同じように、すこしずつきつくしていきます。
原則的に、重なっている二本の下緒が奇麗に重なったまま結んでいくことが大切です。
形が崩れないように注意しながら、きつくする作業を進めて下さい。
このように、右側に二つ、左側に一つできました。
下緒の長さによって、このように調整するようにして下さい。
結束しない場合
続いては刀の下緒をほどいている時の、下緒の処理法を解説致します。
天心流では、第八世師家 石井清造先生曰く「下緒は武士にとってはネクタイのようなものである。登城の際や原則的には、下緒を結束しておくことが嗜みである」と教えました。
しかし実際には下緒をほどくことがあります。結束を解いたときでも、下緒を処理する方法がありますので、それを解説致します。
まず胡蝶結の状態から下緒をほどきます。
この次が非常に重要です。下緒を重ねた状態で、それを鞘に一巻します。そして下緒と鞘の隙間に通します。
これは非常に重要な手順になります。この手順を省いてしまうと、下緒が引っ掛かった場合、下緒を引いた場合に栗形が外れてしまう恐れがあります。また刀が不安定になりやすい、という理由もあるため、必ず下緒を鞘に一巻してから、作業を行います。
この後は、重ねた下緒の先端部を一巻して結束させるだけです。
上に来ている下緒を下から巻き付けて、通します。
このように結ぶだけです。最後は長さを調整してください。
非常に簡単な方法です。これが天心流の結束しない場合の下緒の処理法です。
あまりにこの部分が先端部分に来てしまうと容易くほどけてしまいますので、最低でも下から二寸から三寸(およそ6cm-9cm)ほどの部分で結ぶと良いでしょう。
実際はもう少し上で結んで良いかと思います。例えばこれくらいの位置でも良いでしょう。
何かあった場合はここを引けば外れますので、緊急の場合はすぐに下緒を鞘から外して使うことができます。
以上が、下緒を結束しない場合の処理についてです。

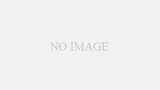
コメント