士道訓 武士訓
一、 一日一生此の命
二、 君主を尊び その下で
三、 我が躰(み)の存在 和愛の生活が
四、 日々の稽古は欠かさずに
五、 家名を盛り立て 武技磨き
六、 己の戒め 流祖の教え
七、 心に刻め 人の世で
八、 私斗 生さば 躰の破滅
九、 主命を守るは 武士の剱
十、 躰に降る邪剱は護躰の剱で
十一、 払って通れ 闇中も
十二、 死生の間も 武技の腕
十三、 石垣崩らば 城立たず
十四、 初覚忘れず 心法も
十五、 主命以外に鯉口切るな
十六、 三尺の秋水(しゅうすい) 手入は欠さず
十七、 願うは天命迎える日まで
これは士林団で唱えられていたという士道訓(武士訓)です。
石井先生が天心先生に読ませて覚えるように命じたものです。
天心先生が思い起こしてこれを記述し、2014年6月15日のFAXでいただき、その後稽古場などで確かコピーを配布して口伝したものです。
半世紀以上前の記憶ですので、細部には間違いもあるでしょうが、大意は変わらないと思います。
次に、各項を解説します。
一、 一日一生此の命
先代曰く「人生は五十年、一日一生の命」。これは日々の一日を一生と思って生きろということです。
信長公も好んだという幸若舞「敦盛」の一節「人間(じんかん)五十年」。昔の人の世は五十年程度と言われていましたが、武士はいつ果てるともしれない戦人であり、一日を一生と思って生きなければならない。
毎日が人生の最後と思って生きるということです。
なお先代は「昔は四十くらいで引退」とも仰っていたとこのFAXを頂いた時に天心先生は仰っていました。
二、 君主を尊び その下で
自らが仕える主君、士林団にとっては徳川将軍、宗矩公などを常に尊びその下で生きるものであると。
さらに先代曰く、君主の下では「民(たみ)隔てなく(平等)」だと含まれるそうです。
三、 我が躰(み)の存在 和愛の生活が
前段にも関係しますが、主君の下ではじめて自分自身は存在出来るものであり、そこに和合と愛に満ちた生活を、民ともどもに送ることが出来るのだと。
四、 日々の稽古は欠かさずに
だからこそ、自らの勤めは主君を守り立てて、和平を紡ぐことであり、そのためにも日々の稽古を欠かしてはならない。
五、 家名を盛り立て 武技磨き
誇れる行いによって、自らの名も、家の名前も日本国中に知らしめる如く努めて、武芸の腕前を磨くこと。
六、 己の戒め 流祖の教え
自分自身の有り様、戒めは流祖から伝わる教えそのものに含まれている。
七、 心に刻め 人の世で
この戒めを心に刻みなさい。もしこの人の世(士林、武士の世)の中で
八、 私斗 生(しょう)さば 躰の破滅
感情的に流されて私闘に走ったならば、身を滅ぼしてしまう。
九、 主命を守るは 武士の剱
主君を守るために用いるのが武士の剣であって、決して利己的な名利(名誉と利益)のために用いる剣ではない。
十、 躰に降る邪剱は護躰の剱で
襲いかかる邪な攻撃も、身を守るための剣を用いて
十一、 払って通れ 闇中も
降りかかる火の粉を払うように、払い正しい道を歩みなさい。
例えそれが暗闇の中の道であったとしても
十二、 死生の間も 武技の腕
生きるか死ぬかという場面でも、武技の腕があればそれを克服しうるものである。
十三、 石垣崩らば 城立たず
石垣とは国(藩)である。この石垣を作る石の一つ一つが藩士である。
もし主君に仕える武士が失われれば国が潰れる元となり、結果、城、つまりその上の民草の生活、自身の名声、家の繁栄、そして国の繁栄も不可能なこととなる。
十四、 初覚忘れず 心法も
初心の教えを忘れずに、そして軽視されがちな心の働きなどの教えも含めて大切にしなさいということです。
なおこれが七番目だったかもしれないということです。
十五、 主命以外に鯉口切るな
主君の命令がない時には、鯉口を切らないという強い意志を持たなければ、いたずらに抜刀し無益な争い、私闘を起こします。
十六、 三尺の秋水(しゅうすい) 手入は欠さず
三尺の秋水(さんじゃくのしゅうすい)とは刀のことです。
今は刀が長く全長100cm(三尺三寸)~が通常ですが、往時は現代より刀の長さは短めのものが多く、そのため三尺とされているのかと思います。
秋水は秋のころの清らかに澄んだ水です。比喩的に、曇りがなく清らかなものでに、よくとぎすました刀を意味する言葉として用いられました。
刀の手入れを欠かしてはいけないと教えています。
十七、 願うは天命迎える日まで
いかなる形でかわかりませんが、毎日を一生と思い、主君に仕えているうちに、いつか生を終える日が来ます。
その日までこの心得を忘れずに武士として気高く生きるということです。
天心流初学集に書きましたが、武士道が現代において必ずしも賛美されるものではありません。
時代錯誤と呼べる部分も多く、決して手放しに受け入れるべきものではありません。
ですが、伝統文化の保存者として、これを大事とする以上、その思想性にも触れて、完全ではないまでもこの心得の一端でもその身に入れなければ、やはり天心流という兵術を深く修養するのは難しいことと言えるでしょう。
世間では美化された武士道が盛んに喧伝され、現実と乖離した、非実在の、往時の教えですらない武士道に訓育を受けた武術家が、跳梁跋扈しています。
そしてそうした妄想的武士道に由来した中傷を天心先生は長年に亘って受け続けてきました。
そうしたトラウマから、天心先生には半ば武士道アレルギーのようなものが醸成され、それは門人にも広まっていました。
しかし私が入門後、学ぶほどに天心流の基本には、士道が深く根ざしており、これは切っても切れないものだと理解するようになりました。
天心先生がこの士道訓を思い出したのは、2014年、私が入門して六年目のことです。
こうしたまとまった形で示されたことは、当時大変感動しました。
これを自らが江戸期の柳営護持の武士として生を受けた者と仮定して捉え、心身に深く受け止めることが出来れば、流儀の技法が自ずと深く刻まれて、自ずとその理解度、解像度は高まります。

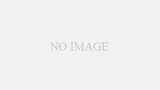
コメント