釣抜(つりぬき)
これは初学 点抜に分類され、鞘を返して抜刀し、抜刀しようとする対者の小手を切り留める技法です。
楷書(守)での抜刀
今回は点抜の一つである釣抜(つりぬき)をご紹介いたします。
その前に、釣抜の状況について説明していきたいと思います。
状況としては、自分が相手と出会い、挨拶をします。礼をしているときに、相手が刀に手を掛けようとします。その状況に自分が対応する技が釣抜となります。
それでは釣抜を行います。
まず真の礼を行います。
真の礼を行っている最中に相手が刀に手を掛けます。
そこで、まず自分も刀に手を掛け、刀を返し、上に抜いていくようにしながら相手の小手を切ります。そして青眼の位になおります。
残心の後、血振るい、納刀を行います。
納刀に定めはありません。今回は転柄血振るい、そして逆手納刀を行います。
横からご覧下さい。
まず真の礼を行います。
真の礼を行ったのち、刀に手を掛け、刀を返し、前に刀を抜いていきます。
刀を前に抜いていきますが、途中から刀を上に上げていくようにし、相手の小手を切り上げます。
切り上げたのち、青眼の位になおり、残心をとっていきます。
反対からご覧下さい。礼をし、刀を返し、切り上げていきます。このとき、横から自分の耳が見えるくらいまで腕を上げるようにしてください。
頭の位置について、ここの状態から上目遣いで相手の状態を認識することができますので、頭は上げないようにして下さい。
納刀の注意点
納刀についての注意点を説明致します。
今回の釣抜や他の技には、このように刀を返して抜く動作があります。その場合、このまま納刀しようとしますと、刀の反りと鞘が合っていないので納刀することができません。そのため、必ず鞘を元の位置に戻す必要があります。
天心流では刀の鞘が返っているかどうかを確認するために、左手を鞘に沿えるようにして、栗形があるかどうかを確認します。
左手で鞘に触って栗形がなかった場合、これは鞘が反転している、上下が逆になっているため、ここで鞘を返すようにします。
稽古するにつれて、このように栗形を確認しなくても、経験則的に「この技法では鞘が返っている」と判断でき、自然に鞘を返すことができます。
今の段階では身体にそのような経験がないと思いますので、左手で鞘の栗形を確認し、栗形がなかった場合は鞘を返す、という手順で納刀を行うようにして下さい。
また、このように目で見て鞘が反対になっていないかどうかを確認することをついやってしまいがちです。この場合、相手から目線を外しているのでとても危険です。そのようなことのないように、左手で栗形があるかどうかを確認し、そして鞘を戻し、納刀するように、普段の稽古から心がけて下さい。
名称の意味について
釣抜の名前の意味ついて解説致します。
釣抜の釣りはFishing、魚を釣るという意味です。
刀で相手の小手を切り上げた後のこの姿勢において、腕は釣り竿を、刀は糸を表しています。そして実際に刀が当たっている部分を獲物とみなしており、この全体の形から釣りをしているような姿である、というところからこの技法の名前を釣抜と呼びます。
注意点
相手の小手を切る際の注意点を説明します。
礼をし、相手が刀に手を掛けます。その瞬間に我は刀を返し、相手の小手を切り上げます。この時に、ここで止める、ということが大事です。
そのまま切り上げた方がいいのではないか、と考えてしまいがちですが、ここに技法の特徴が出ています。
ここでバシッと切り込むような形でストップします。これを天心流では「戸と戸の間に指を挟んだらとても痛い、そのような切り方になる」と表現しています。
もしも止めずに切り上げますと、小手に当たった場合、当たらなかった場合、いずれも共通して刀が相手の喉や顔に突き刺さります。また相手が刀を上げた際は、そのまま自分の刀が下に行ってしまいます。
突き上げるように切る、という動作には様々なデメリットがあります。
この技法では相手を殺すことを目的とはしていません。そのため、あくまでも小手を切り、その後、相手の状況をふまえつつ止めます。これは活人剣(かつじんけん)の意味を含んでいます。
強く切ってしまいたい、という気持ちはあるものの、小手を上げることで、拳を高く上げることで自然と刀の切っ先が働くようにし、相手の小手を切り、また刀が止まるようにします。
その部分に注意をしながら、稽古を進めて下さい。
草書(離)での抜刀

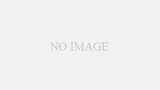
コメント