坐法、立相に限らず、股関節を開くというのは 非常に重要な動作です。しかし床座文化から離れた現代人にとって、坐 法での開脚は特に難しい動作となります。そのため両膝の開閉のみを抜き出した稽古法を紹介します。なおこれは伝統的な稽古法ではありません。
代表的な使用例
膝の開脚で、初学者にも馴染み深いのが坐法 小太刀抜刀術の抜刀(ぬきうち)でしょう。
抜刀(ぬきうち)では、まず両膝を閉じつつ抜刀し、切り下ろしで両膝を出来るだけ開きます。
沈み青眼の際に、再び両膝を完全に閉じます。
注意点として、両膝を開いた際に、両太ももが後傾してはいけないとうことです。
両膝を開いた際に、両太ももは垂直を維持するようにします。
両太ももを後傾させると、膝はより開きますが、腰が潰れて姿勢が崩れてしまいます。
骨盤(腰)が後傾して力が逃げてしまい、次の動作に移る際にも遅れが生じます。
両太ももが垂直(僅かに前傾する場合もあります)だと、膝は少し狭くなりますが、正しい姿勢となります。
動作解説
まず両膝を閉じます。
腰を浮かせてつま先立ちとなり、上体を垂直にします。
極力骨盤を後傾させないように注意しつつ、出来るだけ両膝を横に開きます。
両膝を完全に閉じます。
そして膝の開閉を繰り返します。
出来るだけ両膝を開きますが、両腿は垂直を維持します。
腰、または臍を前に突き出すように意識すると正しい姿勢が取りやすくなります。
両膝を閉じた際にも、上体と太ももは出来るだけ垂直を維持します。
実際には、やや腰が僅かに前に突出するような弓なりの姿勢となります。
終わりに
天心流で必要な股関節の可動域を高める上で、効果的な稽古法になります。
こうした部分練習は、正しい動作を短期的に、そして効率的に身につける上で大変効果的です。
この膝の開脚についての方法の指定はされていませんが、部分練習自体は天心流で行われる通常の稽古法の一つです。
回数に定めはありませんが、一度に20回を1セットとして3セットほど行うと良いでしょう。
序破急の三段階の速度で行うとより効果的です。
天心流には多くの技法・稽古法があるので、毎日行うよりも、週に一回など折に触れて行うと、バランスよく身体機能と技術を身につけることが出来ます。

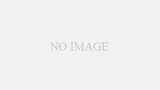
コメント