立ち上がり方
みなさんこんにちは、井手柳雪(いでりゅうせつ)です。
TENSHINRYU ONLINEのメンバーの皆さんがFacebookに動画をあげてくださっていること、とても嬉しく思っています。
鍬海先生と私は皆さんが上げてくれた動画をしっかり見ています。
皆さんの動画を見ると、やはり技や所作に修正すべき点が見受けられます。修正すべき点については、私たちのコメントや、あるいはこれから私たちが折に触れて上げていくブラッシュアップ動画を見て直して頂ければと思います。
技や所作の修正は皆さんだけでなく、もちろん私たちも日々常に考えています。
稽古というものには終わりがありません。私たちは常に上を目指し、今日は何が悪かったのか、どのようにしたらもっと良くなるかを考えながら稽古をしていっています。
ですから皆さんも私たちと同様に稽古を続けていっていただき、お互い上達していって頂ければと思います。
さて、以前座り方について解説いたしましたが、今日は立ち上がり方について詳しく解説していきたいと思います。
立ち上がり方は大刀を持っている状態での立ち上がり方、大刀を持たずに脇差だけ腰に差している状態での立ち上がり方の二種、また通常の立ち上がり方と提灯立(ちょうちんだち)と呼ばれる立ち上がり方の二種があります。
前者の二種、後者の二種、合わせて四種の立ち上がり方について今回は説明していきます。
提刀(さげとう)での立ち上がり方
手で刀を持っている状態での立ち上がり方について説明いたします。
以前の動画で刀の持ち方について説明した際に、
侍(さむらい)は往時の日常生活では栗方(くりかた)より下に手を掛けて刀を持つ、
また稽古中や演武中ではこのように右手の親指で鍔を控えて刀を持つ、と説明しました。
これから立ち上がり方について説明する際には、全て右手の親指で鍔を控えた状態で行います。
往時の日常生活のように栗方(くりかた)より下に手を掛ける刀の持ち方、あるいは右手親指で鍔を控える持ち方、いずれも立ち上がり方には違いはありません。
そのため、これから全て右手の親指で鍔を控えた状態で立ち上がり方について説明していきます。
では実際に立ち上がり方について詳しく説明していきます
まず右手の親指で刀の鍔を控えます。
そして刀を右腰につけます。
次に両膝を閉じながら、つま先立ちになります。
右足を半歩前に出します。
体を起こして立ち上がり、先ほど前に出した右足を後ろに引きます。
最後に右手、左手を下ろします。
続いて横からご覧ください。
刀を右腰につけ、両膝を閉じながらつま先立ちになります。
右足を半歩前に出し、立ち上がり、右足を後ろに引き、刀を下ろします。
概略を説明いたしましたので、次に特に注意してほしいことについて説明していきます。
まず、鍔を膝頭の位置に合わせた刀の置き方、また柄頭を膝頭の位置に合わせた刀の置き方、どの刀の置き方でも立ち上がり方は共通で、違いはありません。
そして刀を右腰につけるとき、あまり刀を上げすぎないようにしてください。
また、鞘を自分の身体に付くほどにする、刀の柄頭を右腿の上にくるほどにするのが刀の位置の目安です。
次に立ち上がる時、つま先立ちになりながら、このように両膝をしっかりと閉じることに注意してください。
また、つま先立ちになるときに、真っすぐ身体を立てるようにして下さい。このように前傾してはいけません。
つま先立ちになりながら両膝を閉じ、右足を前に出していく際、ご覧いただいているように右足のつま先が左足の膝を少し超えるくらい、これが右足の位置の目安となります。
このように大きく前に右足を出してしまうと、相手に近づき過ぎてしまいます。そのため、相手と自分との間合いを保ちながら立つように心がけて下さい。
刀を右腰につけ、
両膝を閉じながら、つま先立ちになり、
前傾はせず、右足を半歩前に出し、
相手に近づき過ぎないように間合いを保ちながら、
まっすぐ立ち上がり、右足を引きます。
左足を前に出すのではなく、相手と自分との間合いを保つため、
前に出した右足を後ろに引きます。
これらの注意点を意識して、立ち上がり方を稽古して下さい。
提灯立ち(ちょうちんだち)
続いて提灯立(ちょうちんだち)という立ち上がり方について説明いたします。
この提灯立は先ほど説明致しました通常の立ち上がり方とは違い、右足を前に出さずに立ち上がる方法です。
特に相手との間合いが近い状態、右足を出さない方が良いような状況でこの提灯立が使われます。
提灯立の提灯は往時、日本で使われていた古い照明のことを指します。提灯はこのように上下に伸び縮むことが出来る照明です。
提灯立の提灯というのは足を前に出さずにそのまま上に立ち上がる姿を表しています。ですから、この立ち上がり方のことを提灯立と呼びます。
それでは実際の提灯立の動作について説明していきます。
先ほど説明した通り、提灯立は特に間合いの近い状況で用いられますので、最初に刀を置くとき、柄頭と膝頭の位置を合わせる、間合いの近い状況を想定して稽古を行うと良いでしょう。
右手で刀を持って右腰に付け、極力、前傾しないようにしながらつま先立ちになりつつ、両膝を閉じます。
ここまでは通常の立ち上がり方と同じです。
そこから足を前に出すことなく、上に立ち上がります
そして刀を下ろします。
横からご覧ください
右手で刀を持ち、右腰につけ、
つま先立ちになりつつ、両膝を閉じます。
ここから、やや後ろに身体を傾けながら、足を出さずに立ち上がっていきます。
そして刀を下ろします。
実演
この提灯立は通常の立ち上がり方と比べて足腰に負担がかかりやすいものになります。
しかし、提灯立を稽古することによって、他の技法で用いられている咄嗟に立たなければならない、咄嗟に行動しなければならない動作に必要な足腰、筋肉を鍛えることができます。
ですから、立ち上がり方といえども軽んじず、提灯立という立ち上がり方を稽古して頂ければと思います。
大刀がない時の立ち上がり方
大刀を持っていない脇差のみ差した状態での立ち上がり方について説明します。
この立ち上げ方は大刀を持っているか持っていないか、くらいの違いしかありません。
しかし手の形は違うので、実際に立ち上がり方を示していきたいと思います。
つま先立ちになりつつ、極力前傾しないようにしながら両膝を閉じ、
右足を半歩前に出し、
立ち上がり、この状態で終わります。
手の形に注意して下さい。開手(ひらで)という形になります。
実演

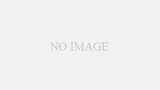
コメント