江戸時代、床座文化が日常的だった人々と、椅子座文化を主体とする現代人では、土台となる足腰の強さに大きな差異があります。
これが現代人の天心流修得を阻害しているのは疑いようのない事実です。
そのため、現代に即した形での稽古法が必要となります。
今回は初学者が、坐法の稽古において最初の難関となる動作の稽古方法を種類します。
なおこれは伝統的な稽古法ではありませんのでご注意下さい。
非常にシンプルな動作ですが、坐法における稽古はこの動作が当たり前に行えるのが前提と言えます。
そしてこのシンプルな動作は、坐法のみならず立相においても重要な役割を果たします。
基礎稽古として繰り返し行うようにして下さい。
動作解説
まず両膝を閉じます。
次に腰を浮かせてつま先立ちとなり、上体を可能な限り垂直にします。
そしてお尻を両踵の上に乗せ、跪坐(きざ)の姿勢になります。この際にも上体を可能な限り垂直にします。
続いて上体を垂直に維持したまま、腰を浮かせます。この際、大腿部も垂直を意識します。
そして上体と大腿部を垂直に維持したまま、両足の甲を床につけます。
最後にお尻を両踵の上に乗せ、端坐(たんざ)の姿勢になります。
注意点
上体を起こす際には、出来るだけ脚力に頼らないように注意します。
後方からお尻を押される、またお尻を前に突き出すような感覚で行います。
また跪坐となった際には、足裏を出来るだけ垂直に立てます。足首の柔軟性が大事です。
この動作には足首の柔軟性が求められます。
入浴時など、足首のストレッチを行うようにして下さい。
終わりに
回数に定めはありませんが、一度に20回を1セットとして3セットほど行うと良いでしょう。
ただし、くれぐれも無理は禁物です。膝、足首などに違和感を覚えたら即座に中止して下さい。
天心流には多くの技法・稽古法があるので、毎日行うよりも、週に一回など折に触れて行うと、バランスよく身体機能と技術を身につけることが出来ます。

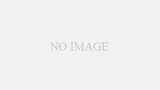
コメント