天心流の外物(とのもの)に含まれる長物(ながもの)、槍、薙刀の概要、稽古における注意事項と礼法についての解説です。
実技以外のこうした要素は、流儀を学ぶ上で大前提となる重要なものです。
今回は、天心流兵法の外物(とのもの)に含まれる長物の取り扱い、ならびに概要を解説していきます。
外物(とのもの)について
刀以外の武器や、武器そのものを使わずに無手でどのように戦うか、というような教え全般のことを外物(とのもの)と呼びます。
長物(ながもの)について
外物に含まれる長物とは、長尺の武器のことを指し、槍と薙刀の二種類です。槍は素槍(すやり)、十字鎌槍(じゅうじがまやり)、そして片刃槍(かたばやり)の技法が含まれています。
今回は長物、基本的には素槍としての扱い方をいくつか紹介していきたいと思います。
それではまず、長物の簡単な説明をしていきます。
天心流の稽古では、剣術を一定以上修めてから次に長物を稽古していくのではなく、最初から外物も併行して稽古していきます。
天心流で用いる槍の長さは定寸は九尺、270cmになります。しかし最初から長大な物を用いると取り回しを学ぶ際に不都合ですので、最初はこのような手槍(てやり)と呼ばれる短めの槍を使用します。
特に長さに規程はありませんが、140cm~180cm位までのものを各人で用意してもらえればと思います。素槍ですので、先は特に何もつける必要はありません。
稽古の際の注意点
最初に、稽古の際の注意点をお伝えします。
まず槍を伏せます。これを伏槍(ふせやり)と呼びます。
槍を置く場合は基本的に床に直置きはせず、何か枕のような物の上に置くようにして下さい。できるようであれば、壁などに立てかけるなどしておくと、より良いです。
このような鉾台や槍掛けを用いるのが正式です。
この状態を伏槍(ふせやり)と呼びます。
稽古の際は基本的、原則的に脇差と大刀の二本を差したまま稽古を行います。何故なら実戦の侍は常に大小の刀を差しているため、稽古がしやすいからと言って刀が無い状態に慣れてしまうと、実戦の時に刀が邪魔で不覚を取ってしまう、もしくは槍が扱えなくなってしまう恐れがあるためです。
また、股立(ももだち)を取ります。袴の脇開き(わきあき)の下、「相引止(あいびきどまり)」と呼ばれる部分を袴の紐に挟んで引き上げます。左右とも同じように行います。これを「股立(ももだち)を取る」と言います。
往時では、このように袴の裾を袴紐に挟んで引き上げることが多いですが、あまりにも足が大きく出てしまうので、現代では概ね相引止を使った方法を用います。この股立の取り方は、別の機会にまた取り上げたいと思います。
もしも袂のある、袖の長い着物で稽古を行う場合は、たすき掛けを行って、袖が邪魔にならないようにしてから稽古を行います。
そして、刀も槍を使う時に邪魔になる場合、落差(おとしざし)にして稽古を行ったりもします。さらに邪魔になる場合、身体の後ろに回して槍を使う方法もありますが、今回は落差で行います。
長物での礼法
続いては、礼法の紹介を致します。この礼法は、槍、薙刀、共通のものです。
まずは実際にご覧ください。
入場の際は、左脇に槍を抱えて持ちます。
そして左足より進み出て、立ち止まり、槍を正面に置きます。
そして臍前(へそまえ)で右手に槍を持ち変えて、右脇に槍を抱え直します。
立礼の場合、このまま礼をし、身体を起こしたところから演武ないしは試合が始まります。
坐礼の場合、右手に槍を持ち変え、右脇に抱えたのち、左膝を地面につけ、右膝を立てる折敷(おりしき)という姿勢になります。そして折敷の姿勢から、左手の甲を見せる「手甲礼」にて、礼を行います。
そして礼を行った後は、この状態から演武ないしは試合が始まりますので、すぐに位を取る、ないしはすぐに攻撃に移ります。
スタンダードな礼法はこの二種類です。
もう一度、横からご覧下さい。
続いて、終わりの礼について解説します。
基本的な動作は始まりの礼と変わりません。一つの動きが終わった際は、石突(いしづき)で地面を叩くようにして、ひとまずの区切りとします。
そして左足を前に寄せて両足を揃え、右脇に槍を抱え込み、折敷となって礼をします。
その後に静かに起き上がり、そして身体の中心に槍の柄(え)を立て、左手に持ち変えて、左脇に抱えます。そののちに下がります。
通常持つ場合はこのように左手で持ちます。右手で槍を持つとすぐに攻撃がしやすいので、攻撃などをしない平時の場合では、このように左手で持ちます。

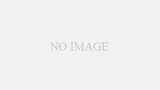
コメント