尖睨抜(とうせんにらみぬき)
これは脅身(きょうしん)の位に分類される技法です。
先代(第八世師家)は心法として「演技が出来なければいけない」と教えました。
技法だけでなく、脅えた姿勢を示すことも重要になります。
楷書(守)での抜刀
こんにちは、連彩(れんさい)です。今日は尖睨抜(とうせんにらみぬき)という技を行います。この技は脅身の位から行います。対者に脅されている状況で、間合いは若干狭目にて技を行います。
それではいってみましょう。
まずは閉足立になります。閉足立から右足を一足分後ろに下げます。そこから右足を右側に若干開いていきます。両手は刀を触らないという意思表示のため、左右に開いていきます。この状態で、相手に対して脅えているような態度を取ります。
これを脅身の位(きょうしんのくらい)と呼びます。
この脅身の位の状態で、脅えながら右足を少しずつ横に動かして退がっていきます。この時、右足は右に移動しますが、重心は左側に残しておきます。この状態で、脅えているかのように後退りしていきます。
対者が刀を抜くや否や、というところで自分も刀の柄に手を掛け、左腕に刀の峰を載せます。
そこから、相手の懐に潜り込むようにして間合いを詰めます。間合いを詰めた後、右腕を下げ、左腕を上げることによって相手の腕を切り上げます。
この状態からの二之太刀は自由ですが、今回は相手の脛(すね)を切っていきます。
右に移動し、脛を袈裟切りします。あとは退がって納刀します。
それでは実際に相手を付けて行っていきますので、横からご覧ください。まず相手が脅してきます。そうしましたら、自分は脅身の位をとります。脅身の位から少しずつ後退りします。相手が行動を起こそうとするや否や、自分も抜刀し、相手の懐に潜り込むように、張り付くように飛び込みます。
飛び込んだ後、てこの原理を用いて、瓶の栓を抜くように、右手を下げ、左手を上げて切り上げます。二之太刀は相手の脛を切ります。そこから退がって、納刀します。
脅身(きょうしん)の位
まずは脅身の位を細かく見ていきます。手の形は指を開いて、若干指を曲げたこのような形になります。このような形で、手の位置はこのあたりです。刀にすぐ手が掛からないように脇は開いて、左右に腕を開きます。
横から見るとこのような位置になります。実際には刀に手を掛けない、ということを示しますが、しかし刀に手を掛けやすいようにするために手を後ろに置かないように、前に置くことが大事です。
続いて足捌きを見ていきます。脅身の位ではまず右足を一歩下げ、右に開きます。この状態で、右足は右斜め後ろへ、重心は左に残したまますこしずつ後退りしていきます。
この時、重心は左に残していますが、重心を若干右に移すことで、相手の攻撃線、この正中から自分の中墨をずらすことができます。そこから左足を前に出していくと、自ずと右側に転ずる(動く)ことができ、相手の正中を外すことができます。
抜刀時のフォーム
抜刀の時のフォームを見ていきます。まずは左手の形です。左手はこのような形をとります。
次に、刀の峰を置く位置を見ていきます。刀の峰を置く位置はこの位置です。左腕前腕のこの位置に置きます。実際は動きや個人差によって刀の位置は若干ずれますが、あまり手首側に来ないように意識することが肝要です。
下半身の形について
次に下半身の形を見ていきます。下半身の形はこのような形になります。相手の下に潜り込むようにして、膝を十分に曲げ、重心を低くします。この時、膝を着くバージョンもありますので、もしも腰を低くすることが辛い方、足に怪我をされている場合は膝を着けても構いません。
切り上げの腕の働き
最後に腕の形を見ていきます。切り上げの時、右腕は下げ、左腕は上げます。この時、左右両方の腕を動かすことが大事です。
技法の名称について
この尖睨抜(とうせんにらみぬき)という名称について説明します。まず、尖(とうせん)、これは刀の切っ先を指します。抜(ぬき)は抜刀のことです。睨(にらみ)は、この時の鍔元から切っ先にかけて相手を睨み付ける、ということから尖睨抜と呼びます。
応用について
この尖睨抜にはいくつかのバリエーションがあります。それを簡単にご覧入れます。
先ほどまでの尖睨抜とは違い、様々な条件下によって若干間合いが離れてしまうことがあります。
そのような場合でも、尖睨抜を使って対応するものです。
先ほどよりも少しだけ間合いが遠かった場合、無理に体捌きを使うのでなく、相手が脅してきて、こちらは脅身の位になり退がり、相手が刀を抜こうとした瞬間、若干前に入っていくことが厳しい場合、刀を若干突き出すようにしながら、刀を抱くようにして、刀の峰を腕に載せて、このようにしながら突き入れます。
立てるようにするときは相手に体当たりするように間合いに入っていくのですが、それが出来ないので、左肘を抱えこむようにして、刀の峰を左の前腕の肘の付根(つけね)近くに載せ、そして切ります。
二之太刀は自由です。
もう一度、素早く行います。切られたところで止まってください。
このような形です。
次はこの条件よりももっと間合いが遠かった場合です。通常攻撃をしてくるということは、このように相手が大きく足を踏み出して刀を抜こうとする姿勢になりますが、思ったよりも相手があまり足を出さずに刀に手を掛けた場合は、思ったよりも間合いも遠くなります。そのような状況ではこのように変化します。
左手首の上に切っ先が載るような形になり、大分形が変わります。突き出すようにして刀を抜き、左手首の上に切っ先を載せるようにして小さく切り上げます。二之太刀は自由で、それは変わりません。
もう一度行います。
以上、簡単にバリエーションを説明致しました。
草書(離)での抜刀

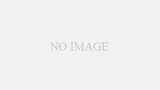
コメント