地蔵抜ブラッシュアップ その弐
地蔵抜のブラッシュアップです。
実戦向きの技法ではありませんが、対面の抜刀におけるエッセンスを学ぶ上で重要な技法です。
こんにちは。今回は地蔵抜のブラッシュアップをしていきます。
膝の働きについて
続いて、膝の動きについてです。
どうしても身体の上半身の動きに着目してしまい、足腰、身体の下半身の動きをなかなか捉えることができていない人が多く見受けられます。そのため、膝の動きに注意して技をご覧ください。
合掌した後に、刀の柄に手を掛けていきます。この時から、膝は緩んでいきます。鯉口を切り、刀を抜いていく際も、より膝を曲げていくことが重要です。
この時の膝の形ですが、正面から見るとなかなか違いがわからないと思いますので、横からご覧ください。
合掌をした後に、刀の柄に手を掛けていきます。この時、膝は曲げていき、刀を抜いていく際には、もっと膝を曲げていきます。
このように、両方の膝が前後するぐらい、膝を曲げることが大事です。
切りの確認方法
これから地蔵抜の稽古法を紹介します。
二本の棒状のものを用意してください。木刀などを代用しても構いません。抜刀する側は袋竹刀(ふくろしない)あるいは木刀などを使ってください。
大体両腕ほどの幅、両肩の広さに両方の棒を持ちます。
抜刀側は良い間合いで立ちます。
そして抜刀し、両方の棒に当たるように切り払います。これを練習します。
実際試斬として行う場合は、二本の巻畳を置いて、本身で切ってみるのも手だと思います。
巻畳を切る場合は、両断はしません。
半畳巻の中心に上腕骨を模した細竹などを入れると良いです。
骨(細竹)を切らない程度を目安に浅く切ります。
実際に二つのものを当てる時には、どうしても一本目には当たるけれども、二本目には当たりにくいという現象が起こりやすいです。
このような感じです。
かといって、一本目に非常に深く切っても、本末転倒になります。実際にそのように切るとここで止まってしまいますから、手の内を巧みに使って、二本目にも当てていくことが重要になります。
手首、手の内の働き
両方の対象を切るときの手の内の働きについて解説します。
この角度からご覧ください。
通常の刀の抜き方ですと、このように右手首を右に曲げて抜くケースが多いと思います。
しかし対面、さらに両方の対象を切らなければならない場合は、右手首をむしろ左に曲げるような心持で行うことが大切です。
地蔵抜の手の内の働きについてお見せします。
刀を抜き、そして右手首を左に曲げるような心持ちです。
地蔵抜のブラッシュアップ、いくつか注意点を今回紹介させて頂きました。ぜひこのブラッシュアップとともに、稽古をしていただければと思います。

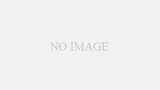
コメント